設計構想書が
書けなくなった理由
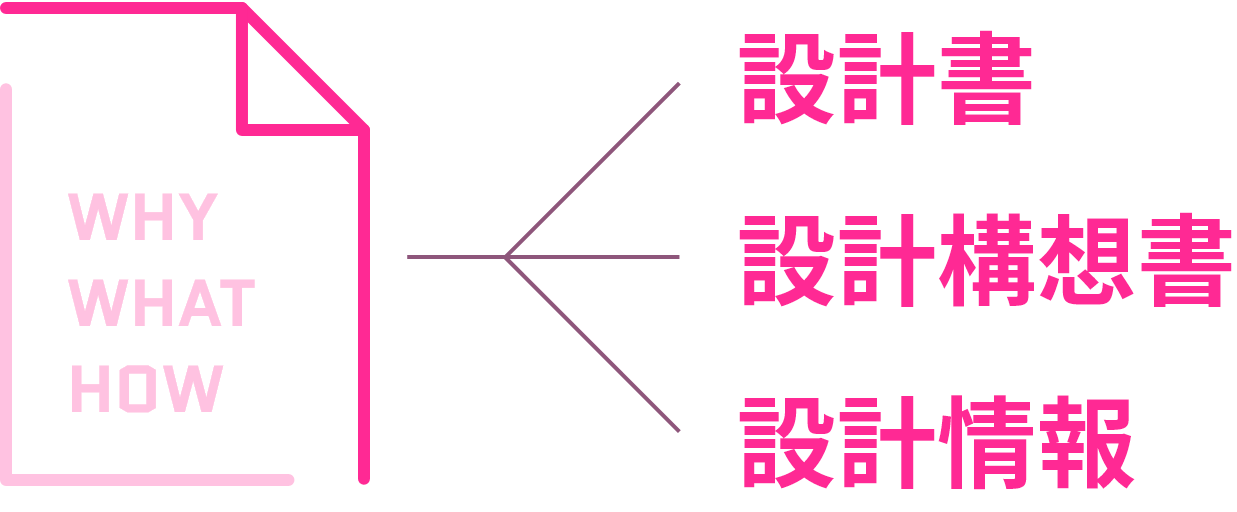
「モノづくり」の時代では、「設計書※」「設計構想書※」「設計情報※」などと呼ばれていたもので、業種、会社間での統一的な名前はないかもしれませんし、会社の標準フローに記載がないから馴染みがないという方も多いかもしれません。
「ものづくり大国」ニッポン。
Japan as No.1 と称されていた頃までの日本の製造業にはまだ残っていて、いまは失ってしまったものは? それが「設計構想書」。「設計構想」とは、物を作るための情報・知識の体系である設計情報と、設計情報が生活者のニーズをどの程度満たしているか? という設計品質が含まれ、商品化する上での指針となるものであり Why,What,How について明確にされているものです。この「設計構想」を描く力は、ゼロイチでものを開発できる新規開発力に等しいものです。
何故、設計構想書が書けなくなったのか?
書けなくなる以前にフローそのものが存在せず書く必要すら無くなったのでしょうか?
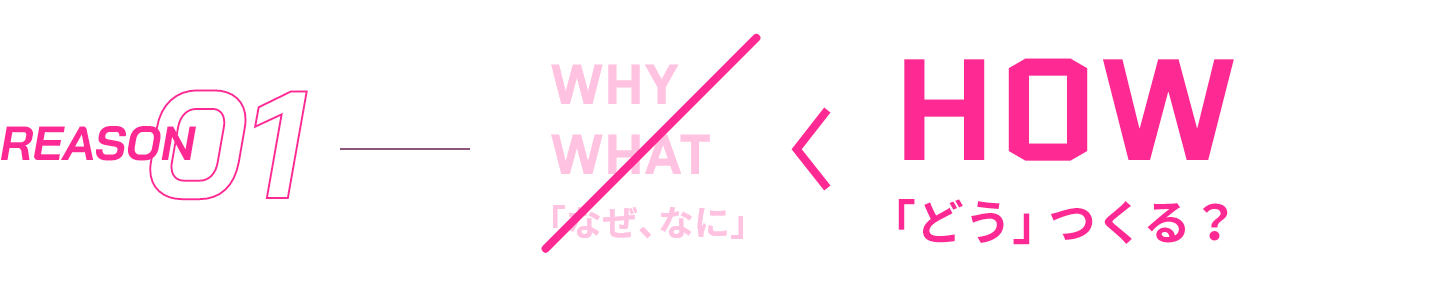
1.製造業として利益重視するあまりHOWばかりに注力してWHATとWHYは気にしなくなった。結果残ったのがHOWだけ。合理化は何かを捨てるコトだとしたら、WHYとWHATを考えることを捨てた。
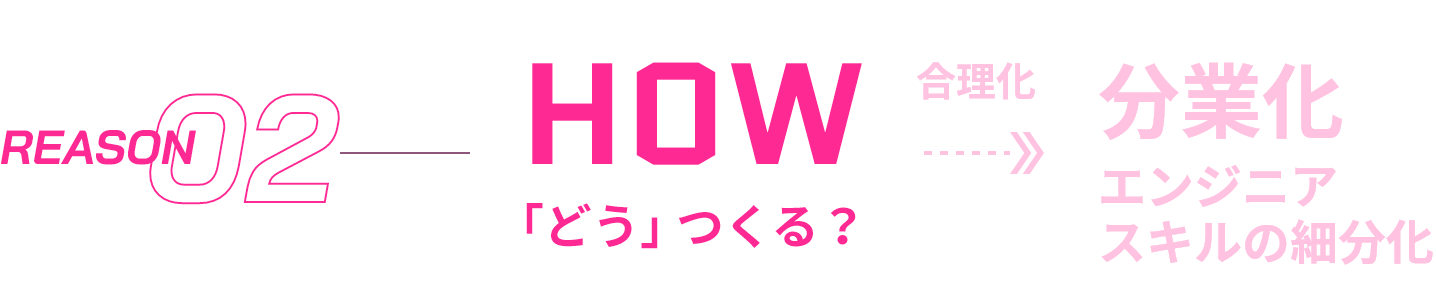
2.HOWの合理化を進め、分業化が進んだ。同時にエンジニアのスキルの細分化が進む。
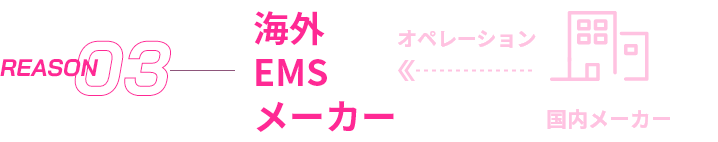
3.ものづくり時代の終盤、低価格化が一気に進み、海外EMSメーカーへのシフトが進む。(OEM、ODM含む)結果、エンジニアとして設計するよりも海外EMSメーカーのオペレーションがメインの業務になり開発スキルは低下。
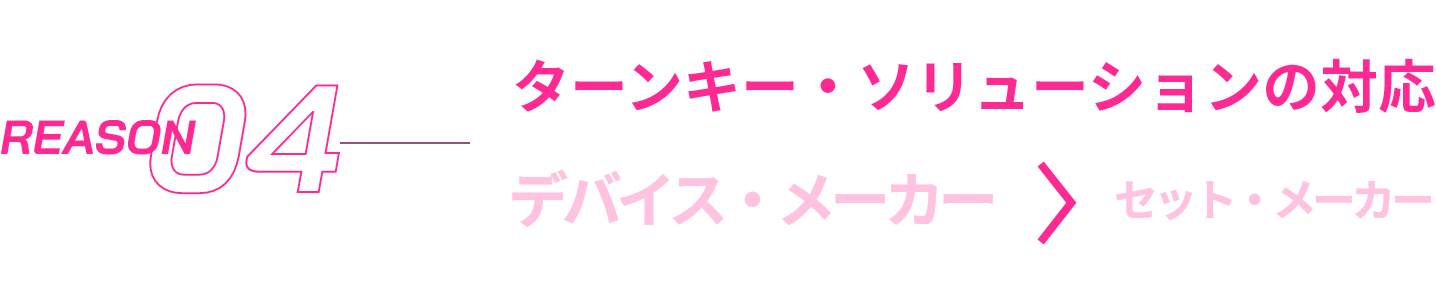
4.メーカーは、デバイスメーカーに具体的ソリューション、ターンキー・ソリューションを求めるようになり、デバイス・メーカーがそれに応える構造になったので、ますますセットメーカーのエンジニアのスキルは低下。一方、デバイス・メーカーも努力するものの本来のセットメーカーのレベルには到達しない。
大きく4つの要因が考えられ、“1”でフローから消え去り、2、3、4を経てスキル設計構想書を書く機会もスキルもなくなりました。一方、時代はことづくりへとシフトし、ことづくりの根源となる設計構想書を書く力が求められています。
注釈
- 設計書 / 設計構想書 / 設計情報
- すべて同じ意味。企業により使用することが違う。設計という言葉を使っているので技術的な内容だけと思われるかもしれないが、「ビジネス・モデル」に関する内容に加えて、商品をどのように企画し、どのようなテクノロジー、キーデバイスを採用して、製造にはどのような工夫をするのか?が一つにまとめられたもの。本文へもどる↑