
「コト」に求められる
「UX (ユーザー・エクスペリエンス) 」
「CX (カスタマー・エクスペリエンス) 」
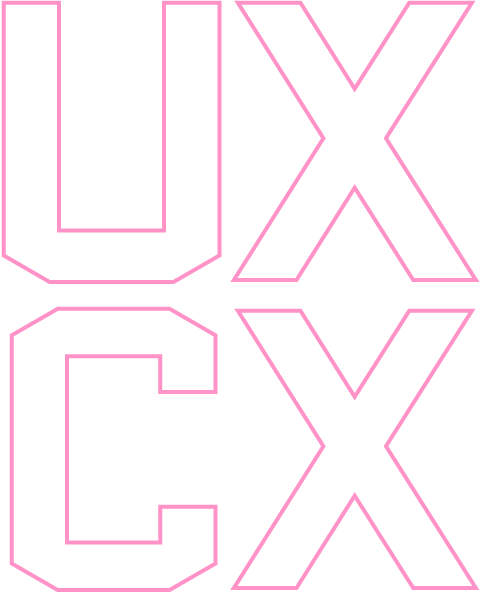
時代は、「モノ」から「コト」へ。
「生活者※」の求める価値は、「モノ」である「製品※」そのものに価値を見出す「モノの価値」から、「商品」の「効用※」、サービスを購入したことで得られる体験に価値を見出す「コトの価値」へシフトしています。
このことは、価値創造の中心が、製品中心の発想から生活者中心の発想にシフトしていて生活者発想から「UX(ユーザー・エクスペリエンス)※」「CX(カスタマー・エクスペリエンス)※」といわれる「コトの価値」を創造することが必要となります。

「モノづくり」から「コトづくり」へ
価値は、「モノの価値」から「コトの価値」へ。
価値のシフトは、製造業に対して「パラダイム・シフト※」が必要であることを意味します。製造業=「モノづくり」は、20世紀を代表する「ビジネス・モデル※」でした。その中心は製品です。より良い製品を、より早く、より安く作っていれば良い時代でした。
21世紀になり、デジタルサービスが主役の時代を迎え、AI・IoTなどのテクノロジーも活用し生活者に価値ある「コト」が中心となり、製造業は、単なる「モノづくり」から「コトづくり」もすることが求められる時代となっています。

さらにその先の「モノ・ゴトづくり」へ
製造業は、「モノづくり」から「コトづくり」へ。
さらに、その先の「モノ・ゴトづくり」へ。
「モノ」から「コト」へ......
「モノの価値」から「コトの価値」へ......
「モノづくり」から「コトづくり」へ......
さらに、その先の、プロダクトアウト(=モノづくり)ではなく、CX / UXをもとにした(=コトづくり)カスタマーインで商品を作り上げる「モノ・ゴトづくり」がこれからの製造業にも求められることです。「モノづくり」と「コトづくり」を両立させること。これが「モノ・ゴトづくり」です。「モノ・ゴトづくり」の時代では、カスタマーサポートではなく、いかに顧客、生活者をつなぎとめることができるかという「カスタマーサクセス※」のマネジメントも必要とされます。
カスタマーサクセスの実践
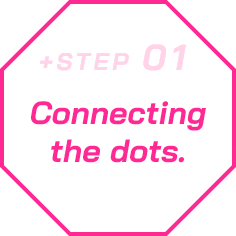
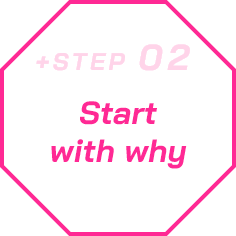
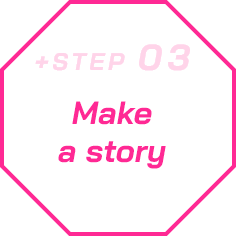
モノ・ゴトづくり
コンセプト





ものづくり
プロセス
「モノづくり」から「モノ・ゴトづくり」へのシフト。
この新しい時代の課題への取り組みのひとつが、「モノ・ゴトづくり」のためのEMS、それが EMSプラスでです。従来型の「モノづくり」のためのEMSから、「コトづくり」を担う3つのSTEPを追加。生活者発想からUX/CXをもとにしたカスタマーインで商品を作り上げ、アジャイル開発も取り入れスピーディな商品開発にも対応。
「モノづくり」の観点では、3+サンプラス の採用によりスマートファクトリー化を実現。「モノづくり」力を底上げ、現代風にパワーアップ。3+サンプラス と EMSプラス 。
「モノ・ゴトづくり」へのシフトを実現し、カスタマー・サクセスを提供します。
注釈
- iPod
- 「デジタル・ディスラプション※」のトリガーとなったアップルが開発・販売した携帯型デジタル音楽プレイヤー。音楽プレイヤー単体のみならず、Apple Music Store、iTunesなどのクラウド・サービス、アプリケーションなども同時に提供し、モノからモノ・ゴトへ、UXと呼ばれる言葉が生み出されるキッカケとなった。iPhoneの原点でもある。本文へもどる↑
- GAFA
- Google、Apple、Facebook、Amazonの頭文字を用いて表記されるITプラットフォーマーの総称。本文へもどる↑
- ICT
- Information and Communication Technology(情報通信技術)の略。ITよりも通信技術によってもたらされるコミュニケーションにウェイトを置いている。日本では、IT が多く用いられているが、ワールドワイドではICTが用いられている。本文へもどる↑
- 商品
- 商いの対象となるもの全てを示す。製品と対比して用いた時に、「モノ・ゴト」を示す。本文へもどる↑
- CASE
- Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Share&Service(カーシェアリングとサービス)、Electric(電気自動車)の頭文字をとって表した造語。「モノ」から「モノ・ゴト」への「モノ・ゴト」を示す。本文へもどる↑
- 生活者
- 商品やサービスなどの財を消費する人を示す消費者という言葉は、マーケティングの観点からみると、「先にモノありきによる企業優先のプロダクトアウト」の対象となる人を示す。UX、CXという「人が、実現したいこと、経験してみたいこと」を表す言葉で用いられる「人」を消費者に対して、生活者という言葉を用いて表す。本文へもどる↑
- 製品
- 材料などを仕入れて加工されたもの。商品と対比して用いた時に、製造業における「モノ」を示す。本文へもどる↑
- 効用
- ここで用いられる効用とは、一般的な「使い道、用途」という意味ではなく、経済学の基本的概念として用いられる効用を示す。多くの機能がある時に、結局、「生活者にとって何ができるようになるのか?」の『何ができる』が効用。本文へもどる↑
- UX(ユーザー・エクスペリエンス)
- UX:(User Experience)の略。「ユーザーが商品(製品やサービス)を通じて得られる体験」を示す。「モノ・ゴト」と同じ。本文へもどる↑
- CX(カスタマー・エクスペリエンス)
- CX:(Customer Experience)の略。「顧客が商品(製品やサービス)を通じて得られる体験」を示す。「モノ・ゴト」と同じ。本文へもどる↑
- パラダイム・シフト
- 今までの考え方や価値観が180度変わること。本文へもどる↑
- ビジネス・モデル
- ピーター・ドラッカーによるとビジネス・モデルとは「顧客は誰か? 顧客にとっての価値はなにか? どのようにして適切な価格で価値を提供するのか」という質問に治する答えであると定義されている。
1.顧客軸:自社の顧客は誰か?
2.提供軸:自社が顧客にもたらす価値は何か?
3.提供手段軸:自社の商品(製品・サービス)をどのように提供するのか?
4.収益モデル軸:なぜ、儲かるのか?
といった4つ軸についてビジネスのあり方を記述したもの。 一時期、利益確保中心の考え方が前面に出過ぎてしまい、良い印象を与えず、あえて「コトづくり」などの造語を用いることも多かったが、最近では、すべてのビジネスモデルの根幹は顧客中心であるという考えを前提に、ビジネス・モデルが論じられるようになった。本文へもどる↑ - カスタマーサクセス
- 顧客満足度という言葉がある時期用いられたが、真の意味でなかなか浸透して実践的に実行されることはなく形骸化してしまった。UX,CX,顧客中心などの考えが再び注目されるいま、受動的に顧客の要望も満たすためだけではなく、顧客の成功と自社の収益とを両立させることを目指して、顧客に対して能動的に働きかけることを示す。本文へもどる↑
- デジタル・ディスラプション
- デジタル技術やそれを用いたビジネス・モデルによって、既存製品・サービスが無くなったり、破壊されたりする創造的破壊を示す。iPodによってウォークマン文化が木っ端微塵にされたのが代表的な例である。「DX(デジタル・トランスフォーメーション)※」によってもたらされる。
- DX(デジタル・トランスフォーメーション)
- 進化し続けるデジタル技術が人々の生活に浸透してくことで、人々の生活がより良いものへと変革すること。単なる変革ではなく、既存製品・サービスを創造的破壊するデジタル・ディスラプションをもたらす。
CONTACT US
EMS+(イーエムエスプラス)のお問合せについて
『EMS+(イーエムエスプラス)の件』とお伝えいただけましたら担当者へおつなぎいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
